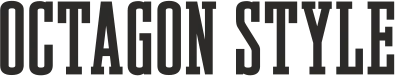「車にサビが出てきたけど大丈夫なの?」
「サビはどのように取り除けばいいのだろうか?」
このような疑問や悩みを抱えていないでしょうか?
車のサビを放置すると、愛車の美観を損なうだけでなく、安全性にも深刻な影響を与える恐れがあります。
本記事では、車のボディにサビが発生する原因や具体的な対処方法、効果的な予防策まで、車のメンテナンスに詳しくない方でも分かるよう解説します。
車のサビについて詳しく知りたい方はぜひ参考してみてください。
Contents
車のボディにサビが発生する原因
車のボディにサビが発生する原因は以下の通りです。
- 飛び石や摩擦による傷
- 鉄粉
- 潮風
- 融雪剤
- 塗装の経年劣化
主な要因を理解することで、効果的な予防策を実施していきましょう。
飛び石や摩擦による傷
走行中の飛び石や接触による傷は、サビが発生する原因の1つです。
車のボディは複数の塗装層で保護されていますが、傷ができると塗装が剥がれ、下地の金属が露出してしまいます。
露出した金属部分に水分や酸素が接触することで、酸化反応が起こり、サビが発生する仕組みです。
特に、以下のような状況では傷がつきやすくなります。
- 高速道路での小石の跳ね上がり
- 狭い道での枝や壁との接触
- 駐車場でのドアパンチ
- 洗車時の不適切な作業
小さな傷であっても、放置することでサビが拡大する恐れもあるため、早めの対策が重要です。
鉄粉
工場地帯や線路周辺を走行する機会が多い方は、鉄粉によるサビに注意が必要です。
大気中に浮遊する微細な鉄の粒子は、車のボディ表面に自然と付着することでサビの原因となります。
鉄粉の発生源はさまざまで、電車の車輪やレールの摩擦、工場での金属加工作業、建設現場での溶接作業などが挙げられます。
車に付着した鉄粉は時間の経過とともに酸化が進み、ボディ表面に茶色いポツポツとした斑点状のサビを形成するでしょう。
湿度の高い環境や海沿い地域では酸化の進行が早くなることもあるため、より注意が必要です。
潮風
海沿いに住んでいる方や海岸地域をよく走行する方は、潮風によるサビに注意が必要です。
海水の塩分を含んだ潮風は、車の金属部分に対して強い腐食作用を持っています。
塩分が車体に付着することで、空気中の鉄粉と化学反応を起こし、急速にサビの進行を促進させてしまうでしょう。
沿岸部で車両や建造物の劣化が著しく進むのは、この塩害による影響が主な要因とされています。
さらに、海岸近くでは潮風と一緒に砂粒が飛散することで、車のボディに細かい傷を作ることもあり、サビが発生しやすい環境といえます。
融雪剤
雪国や寒冷地に居住する方は、冬に散布される融雪剤によるサビに注意しましょう。
道路の凍結防止や除雪効率の向上を目的として使用される融雪剤は、塩化ナトリウム・塩化カルシウム・塩化マグネシウムなどが主成分となっています。
塩は雪を効果的に溶かす一方で、金属に対して強力な腐食性を示します。
車体に付着した融雪剤の塩分は、ボディ表面の鉄粉とあわさることで、急激にサビを進行させるでしょう。
降雪地域では走行後の徹底的な洗車、特に下回りの洗浄が欠かせません。
また、事前の防サビ処理により被害を大幅に軽減することが可能です。
塗装の経年劣化
車の塗装は長期間の使用により徐々に劣化していき、サビの原因となります。
日常的に傷の点検をしていても、時間の経過とともに塗装自体の保護機能が低下してしまうことは避けられません。
紫外線、雨、温度変化などの自然環境に長期間さらされることで、塗装の表面にあるクリア層から徐々に劣化していきます。
また、車体の色合いがくすんで見えたり、光沢が失われたりしている場合、本来持っていた防水性や耐候性が低下していることも考えられます。
定期的なワックスがけやコーティング施工により、塗装の劣化進行を遅らせることが重要です。
車のサビを放置してはいけない理由

車にサビが発生した場合、「まだ小さいから大丈夫」と考えて放置してしまうことは危険です。
サビは一度発生すると、鉄の酸化反応により進行し続ける性質があります。
初期の小さなサビでも、時間の経過とともに範囲が拡大していき、最終的にはボディに穴が開いてしまうこともあるのです。
極端なケースでは、フロア部分が腐食により朽ち果て、室内から地面が見えるほど深刻な状態に陥ることもあります。
また、より深刻な問題となりやすいのが車体下回りのサビです。
この部分は日常点検が難しく、発見時にはすでに重大な損傷が進んでいることが大半です。
車の下回りには、走行の安全性に直結するサスペンション・ブレーキシステム・ステアリング機構などの部品が集中しています。
こうした部分が劣化・破損した場合、正常な制動力の低下や操縦不能を引き起こし、重大な交通事故につながる危険性もあります。
このため、定期的な下回り点検と予防的な防サビ処理の実施が不可欠なのです。
車のボディにサビが発生した際の対処方法
サビがすでに発生している状況では、進行を食い止めるための応急処置が必要です。
作業は以下の3段階で進めていきます。
まず、カー用品店で入手できる専用のサビ除去剤を使用して、サビを除去しましょう。
筆塗りタイプやペーストタイプのものが扱いやすくおすすめです。
サビが深く進行したケースでは、サンドペーパーを併用して物理的に削り取る作業も必要になります。
サビを除去した後は、金属面にサビ止めペイントを塗布することで、サビの拡大を防止しましょう。
また、塗った箇所のサビがサビ止めの被膜に変換する、サビ転換剤と呼ばれるものも存在します。
最後に、車体色に適合するタッチアップペイントを塗ることで、処理箇所を目立ちにくくさせて完了です。
ただし、上記の対処法はあくまで応急的な対処であり、根本的な解決には専門業者での修理が推奨されます。
サビを予防するための方法

ここからはサビを予防するための効果的な方法を5つ紹介します。
- こまめに洗車する
- 下回りに防サビ処理を施す
- ボディコーティングを実施する
- ガレージに保管する
- ボディの傷を長期間放置しない
こうした予防法を組み合わせることで、車を長期間サビから守っていきましょう。
こまめに洗車する
基本的なサビ止め対策として、定期的な洗車があげられます。
車のボディには融雪剤・鳥の糞・樹液・花粉など、日常的にさまざまな汚染物質が付着します。
こうした汚れを放置してしまうと、塗装面にダメージを与えられ、サビが発生する原因となってしまうのです。
ボディの汚れを速やかに除去することで、塗装の保護機能を維持し、サビのリスクを大幅に軽減できます。
中でも重要なのは、ホイールアーチや車体下部など、目につきにくい箇所である下回りの洗浄です。
高圧洗浄機を活用することで、通常のホース洗浄では届かない複雑な形状部分の汚れも除去できます。
また、洗車作業にはボディ全体を詳細に観察する機会が得られるというメリットもあります。
小さな傷や塗装の異常を早めに発見することで、深刻なサビの進行を未然に防ぐことが可能です。
下回りに防サビ処理を施す
車の下回りは、サビが発生しやすい部分でありながら日常点検が難しい箇所でもあるため、専用の防サビ処理を施すことが重要です。
たとえば、海沿い地域では潮風による塩分、寒冷地では融雪剤の塩化物質が車体下部に蓄積され、継続的な腐食の原因となります。
こうしたリスクに対しては、下回りのコーティング処理が効果的です。
コーティングの種類によっては、サビ止め効果に加えて傷を防止する効果も期待できるため、結果的に車両の維持費削減にもつながるでしょう。
ボディコーティングを実施する
ボディコーティングは、車の塗装表面に保護膜を作り、外部からのダメージを防ぐ効果的な方法です。
サビ防止を主な目的とする場合は、ガラスコーティングがおすすめです。
ガラスコーティングは、ワックスやポリマー系コーティングと比較して優れた耐久性を持っており、サビの原因となる微細な傷の発生を抑えます。
また、酸性雨・紫外線・塩分などの物質から塗装を長期間保護する機能も備えています。
自身でできるものもありますが、より高い仕上がり品質と持続効果を求める場合は、専門業者に依頼するようにしましょう。
ガレージに保管する
車を屋根付きのガレージで保管できれば、降雨・降雪・紫外線・鳥の糞・大気中の鉄粉などの環境要因から車を保護しやすくなるでしょう。
ガレージの設置が難しい場合でも、カーポートを設置することで雨や直射日光から車体を保護できます。
さらに、車専用のボディカバーを使用することで、飛散物や汚染物質からも車体を守ることが可能です。
ボディの傷を長期間放置しない
ボディに発生した傷は、小さなものでも早めに修理することをおすすめします。
軽い傷であっても、塗装が損傷して下地の金属部分が露出している場合、そこから酸化反応が始まりサビが発生します。
初期段階では局所的な問題に過ぎませんが、時間の経過とともにサビの範囲が拡大していき、やがて周辺の健全な塗装部分まで侵食していくでしょう。
傷を見つけたら、速やかに専門業者へ相談して適切な修理を受けることで、長期的な車両の安全性と資産価値を維持できます。
まとめ
ここまで、車のボディにサビが発生する原因やサビを放置してはいけない理由、対処方法について詳しく解説しました。
車のサビは飛び石による傷・鉄粉・潮風など、さまざまな要因で発生します。
放置すると安全性の問題や高額な修理費用につながる恐れがあるため、小さなサビでも軽視してはいけません。
予防対策としては、こまめな洗車・下回りの防サビ処理・ボディコーティング・適切な保管環境の整備が効果的です。
サビに対する適切な対策をとることで、安全で快適なカーライフを送りましょう。